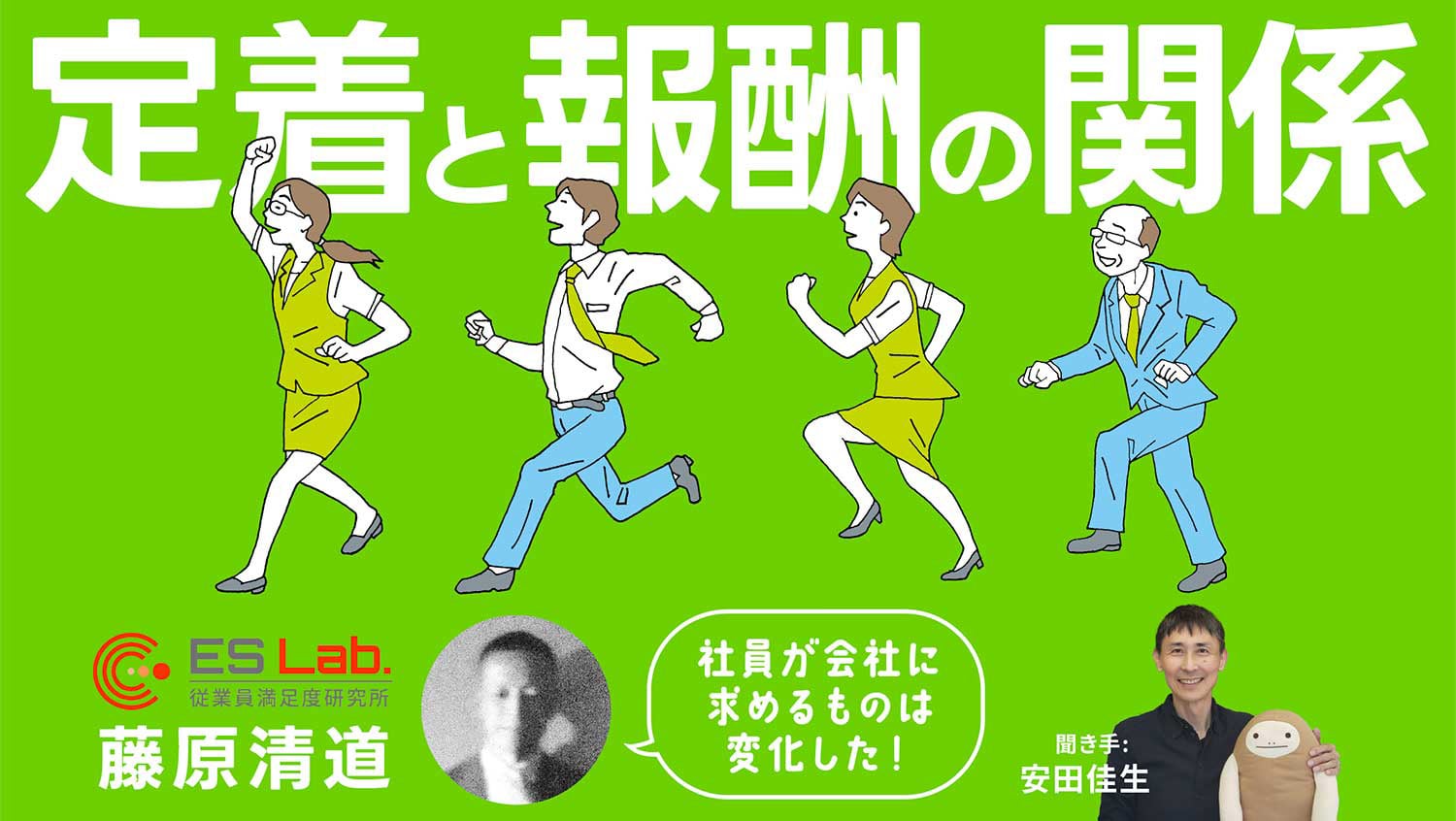会社役員 近藤 稚津子 様
- 代表ではないという理由で「最終判断は社長」と、自分で決めきれないスタンスに甘んじていた。
- 結果として、組織に変化を起こせない自分に気づいていなかった。
- 組織運営において、ES(従業員満足)や価値観共有の優先順位が不明瞭だった。
- クレドやESの本質について、概念レベルの理解にとどまっていた。
- 幹部として「自分が変えなければ変わらない」と腹落ちした。
- 「新しいルールを自ら作る」行動的姿勢への転換が始まった。
- 利益優先ではなく、ESを判断軸に据えることの重要性を理解した。
- ミーティングなど現場判断にもESを活かす意思を持ち始めた。
- 組織として「選ばれる存在」になるための道筋をイメージできるようになった。
- 採用後も「知ろうとする姿勢」が重要であることに気づいた。
- 「これぞという人を採ったらOK」ではないと認識できた。
心からの感謝と、最も大きな気づき
この度はこのような貴重な動画をご提供くださり、本当にありがとうございます。
今回も多くの気付きを得る事が出来ました。
最大の気付きは、自分の覚悟がまだまだ足りないということです。
幹部という立場にいながら、代表ではないという理由で、
「最終的な判断は社長がするもの」とどこかで頼ってしまい、
自分で決めきれない弱さを抱えていたことに気づきました。
これでは、何も変えることができなくて当然です。
受け身のままでは、組織にも自分にも進化はない。
自分で新しいルールをつくるくらいの行動力を持たなければならない。
その覚悟を改めて強く意識する機会になりました。
特に印象に残った学びのメモ
▶ なぜ人は組織に集うのか?
今は、組織に属さなくてもお金を稼ぐ手段はいくらでもある時代です。
それでもなぜ、人は組織に「働きに来る」のか?
その理由として挙げられたものが、深く胸に残りました。
・自己実現に向かって行動する意欲
・組織の力で、大きな仕事を成し遂げたいという想い
・レベルの高い人と働きたいという願い
・仕事と人を重視しているという価値観
こうした思いを持って入ってきてくれたスタッフに対して、
私は本当に、やりがいのある仕事を与えられているのだろうか?
そう自問せずにはいられませんでした。
「これぞ!」と思う人を採用できたからといって、
その後の組織づくりが機能するとは限らない。
むしろ、そこからが本当のスタートなのだと痛感しました。
▶ 経営判断における優先順位
印象的だったフレーズがあります。
【ビジョンや理念に共感し、共に行動してくれる人の幸せを追求する】
【経営者の満足はいくらか後回しにする】
この価値観の優先順位が、経営や現場判断の軸として大切だと再確認しました。
目先の利益や効率ではなく、人の幸せが起点となるような判断ができているか?
今後も問い続けていきたいと思います。
▶ 居心地の良い組織とは誰にとってか?
【頑張っている人にとって居心地の良い組織にすること】
【逆に、頑張っていない人にとっては居心地の悪い組織にすること】
これは単なる厳しさではなく、
「どんな価値観で組織をつくっているのか」を明確に示す姿勢だと受け取りました。
結果、組織としての一貫性と、公平さが守られるのだと思います。
▶ 経営者の“根っこ”は、見抜かれている
強く印象に残った一言がこちらです。
【従業員は経営者の本音と建前を見抜いている】
これはまさに、真実だと思いました。
だからこそ、採用活動の時点から、
自分自身の価値観をオープンにすることが不可欠です。
・自分の頭の中は、他人には見えない
・思っていることは、正確には伝わらない
・「言ったからOK」ではなく、「伝わったかどうか」が大切
・人間は、疑わしいことを悪い方向に解釈する生き物
・価値観が合わない人を放置せず、対話していく姿勢が必要
これらの視点を持ち、採用や人材育成に取り組むことの大切さを再認識しました。
クレドの本質と、ボトムアップ型の文化づくり
価値観を共有するためのツールとして「クレド」がある。
その言葉の重みと意味合いを、改めて深く理解できました。
【クレドは、ボトムアップ型の価値観軸を表現できるツール】
トップダウンではなく、現場主導・対話主導で文化をつくりたい会社にとって、非常に有効な手段であると感じました。
・アウトプットの品質(QC)が揃いやすくなる
・社内コミュニケーションに一貫性が生まれる
・組織全体のベクトルが揃う
・結果として、“選ばれる企業”になる土台ができる
単なる理念の言語化ではなく、
文化形成と選ばれる組織づくりを可能にする道具として、クレドの価値を捉え直すことができました。
ES(従業員満足度)は手段ではなく目的でありたい
最後に、自分の中で最も大きく残ったのはこの一言です。
【ESは手段ではなく、目的である会社で私は在りたい】
この言葉に出会えたことで、
今後の行動指針が明確になったように思います。
会議やミーティングで何か違和感を覚えたとき、
「利益が出るからやろう」ではなく、
それによってESが下がってしまわないか?
その視点を常に持ち、必要であれば
“ESを守る提案”ができる幹部でありたいと強く思いました。
「ESは目的ではなく手段」になってしまっていないか?
あるいは「目的として捉えているつもりで、実際には手段扱いしていないか?」
その違いと意味を、スタッフとも共有していきたいです。
他のお客さまの声
当社の「従業員」の定義
当社では「従業員」を“理念やクレドに従う全スタッフ”と定義しています。
つまり一般的な社員だけでなく、アルバイトさん、パートさん、
そして経営トップや役員も従業員の一人であり、そこに優劣はありません。
一般的には、経営者に「従う」という意味で従業員という言葉が使われていますが、
当社では理念やクレドに「従う」という意味で、
経営トップも含めて関係者全員を従業員と定義しているのです。
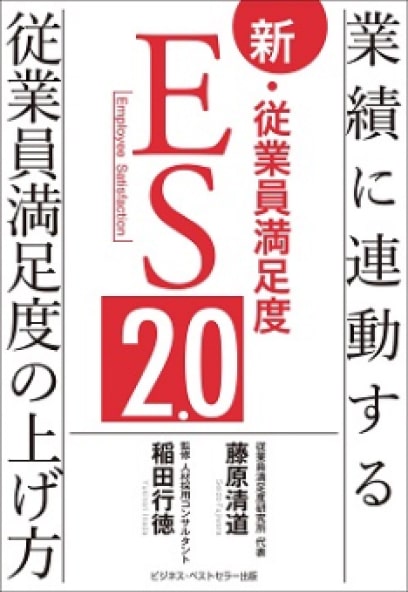
手軽に学び始めたいという方はこちら
日本で唯一の
ESに特化したメルマガ
2008年の創刊以来、毎日配信し続け6230号。
採用や組織作りを中心とした現役経営者の思考を学べる
1ヶ月間無料の日刊の会員制メールマガジンです。
サービスについてご質問などがございましたら、こちらからお問い合わせください。
お問い合わせはこちら