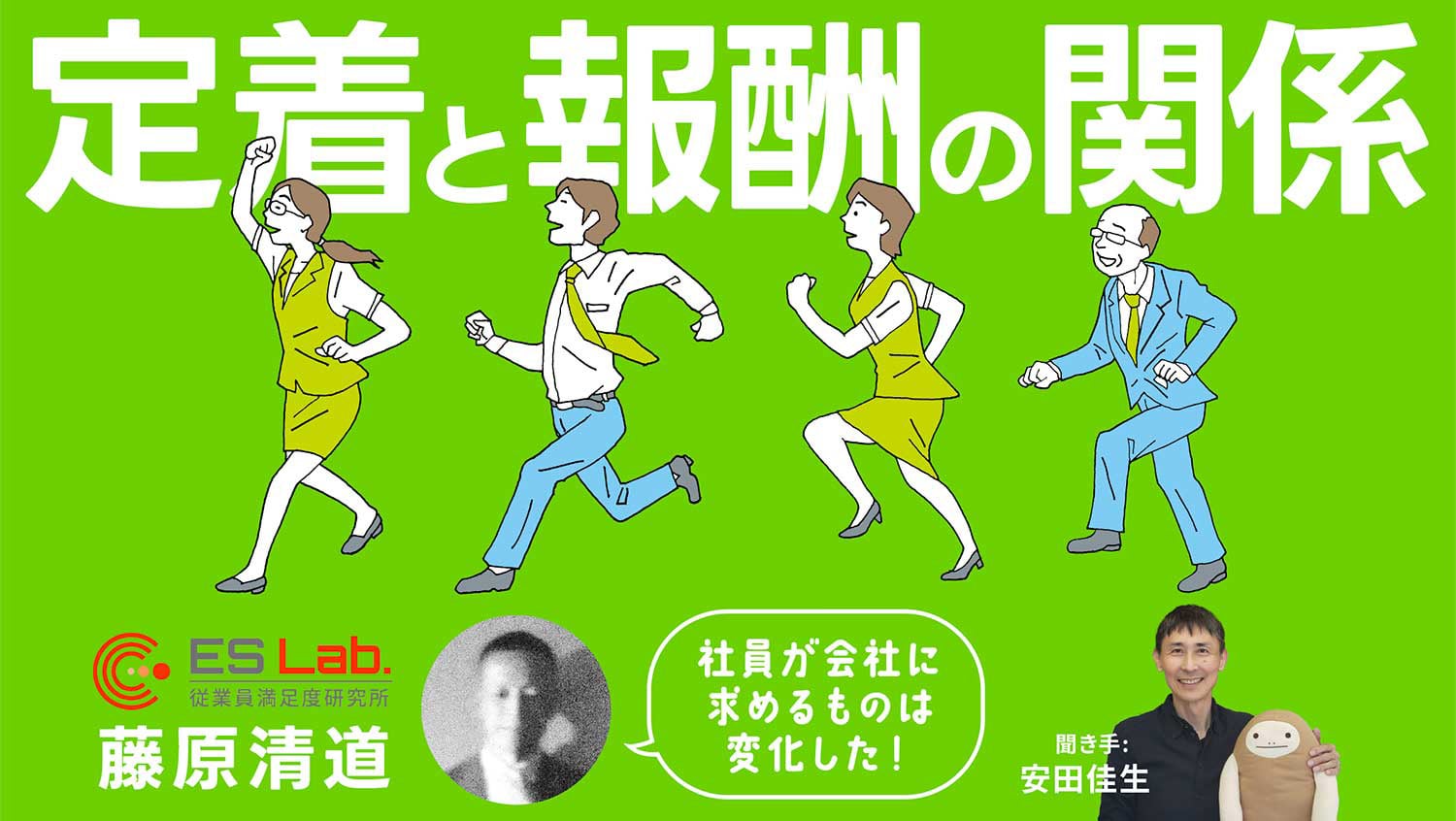真夏の日本を飛び立ち、約10時間のフライトで冬のシドニーに降り立ちました。半袖で汗ばむ日常から、ニットや冬用のジャケットが必要な街へ──その瞬間、地球の広さと不思議さを身体で感じました。
知識としては知っていた季節の逆転を、こうして皮膚感覚で刻みつけたのは初めてです。目を閉じて開けた瞬間、まるで別世界にワープしたような感覚。南半球は私にとって未踏の地で、その光景は美しくも、やがて重たい影を帯びて見えてくることになりました。
6万年の暮らしを変えた1788年


この大地には、約6万年以上にわたり、アボリジナルと呼ばれる先住民が暮らしてきました。肌は黒に近い濃い茶色で、独自の250以上の言語と文化を持ち、土地との精神的なつながりを中心に生活を営んできた人々です。
それがわずか240年前──1788年1月26日、イギリスの第一船団(First Fleet)がシドニー湾に上陸した瞬間から一変しました。この日は後に「オーストラリア・デー」と呼ばれますが、先住民にとっては「侵略の日(Invasion Day)」です。
イギリスはこの地を「無主地(terra nullius)」と宣言し、現地の同意も交渉もなく流刑植民地としました。以降、18世紀末から19世紀にかけて、囚人だけでなく自由移民も増え、白人の定住が急速に進みました。
奪われた命、土地、言語

この過程で、武力による虐殺とヨーロッパから持ち込まれた天然痘・麻疹・インフルエンザなどの感染症がアボリジナルを襲いました。免疫を持たない彼らは急速に人口を減らし、推計75万〜100万人いた人口は1900年にはわずか6万人にまで減少しました。
生き残った人々は、19世紀後半から20世紀にかけて進められた「白豪主義(White Australia Policy)」のもと、英語以外の使用を禁じられ、文化や儀式も抑圧されました。さらに、1910年代から1970年代まで続いた「盗まれた世代(Stolen Generations)」政策により、多くの子供が親から強制的に引き離され、白人家庭や施設で育てられました。自分の名前も部族も言語も知らないまま成長した子供たちは、大人になってから「自分が誰なのか分からない」という深い空虚感を抱えたといいます。
こうして、白人が多数派を占める社会構造が形成され、英語が公用語となりました。それは自然な成り行きではなく、武力と制度によって意図的に作られた秩序だったのです。
英語はなぜ広まったのか

英語は美しいから世界共通語になったのではありません。それを話す国が世界を支配していたからです。
19世紀末、イギリスは「太陽の沈まない帝国」と呼ばれ、世界の陸地の約25%、人口の4分の1を支配していました。英語はその植民地支配の道具であり、オーストラリアでも先住民の言葉を教育現場から排除し、「正しい言語」として英語だけを植え付けました。
ブルーマウンテンズの青い霞を眺めながら、その構造を骨の髄まで感じました。ユーカリの葉の揮発性オイルが太陽光で反射して生まれるその青さは美しい。しかし、この地もまた、アボリジナルの聖地であり、1813年に白人探検家が横断して以降、西部への開拓と資源採掘が進み、多くの命と文化が奪われた場所です。
The sun never sets on the British Empire.

The sun never sets on the British Empire.「太陽の沈まない帝国」というこの言葉。イギリスの植民地は地球上のあらゆる場所に広がり、どこかで必ず太陽が昇っている、という誇示的表現です。帝国の規模を誇り、征服を正当化している響きが、この言葉からにじみ出ています。
世界最大規模の植民地支配を誇っていた当時のイギリスは、いまロシアの軍事侵攻を非難する一方で、自国の歴史的な侵略・植民地支配の責任についてはほとんど語りません。そのダブルスタンダードぶりを、日本国政府も日本のメディアも知っていながら、公に口にしない姿勢を貫いています。誰に遠慮しているのか、どこに忖度しているのかは分かりません。
イギリスは歴史的に「二枚舌外交」「三枚舌外交」と呼ばれるような矛盾した外交政策を同時進行で行ってきたことで知られています。日本がイギリスに遠慮する必要は、本来まったくないのです。
百歩譲って、過去のイギリスが行ってきた非人道的な行為には一時的に目を瞑るとしても、現在のイギリスもまた、人権や国際法を掲げながら自国企業の利益のために強権国家と取引をするしたたかさを持っています。民主主義を語りながら、サウジアラビアなどの権威主義国家と軍事提携を結ぶ姿は、現代の「二枚舌外交」と言ってもよいでしょう。
それでも、日本人の中には英国(イギリス)や英語(イングリッシュ)に強い憧れを持つ人が少なくありません。なぜ、正しい日本語を流暢に話す人よりも、英語を流暢に話す人に憧れたり、英語を話すだけで「優秀な人」という認識をするのでしょうか。
ハリー・ポッター、シャーロック・ホームズ、ロイヤルファミリー、ザ・ビートルズ…。教育や文化を通じて「整えられた魅力的なイギリス像」が積極的に日本に伝えられてきましたが、イギリスが行ってきた加害の歴史は、学校教育でもメディアでもほとんど語られることはありません。
そして英語は、世界の支配言語として発展した結果、国際ビジネスや学術、科学などの共通言語となりました。昨今は、日本国内でも英語を社内公用語にする企業が現れ、私たちは英語を「中立的な便利ツール」のように考えがちですが、実際には暴力的な歴史とともに拡大してきた言語なのです。
英語とその背景を知ること

私たち日本人が、現代の世界をつなぐ言語である英語を学ぶことは、とても良いことだと思います。しかし、盲目的に英語に憧れ、「英語を話せる人はすごい人」と思い込むようなことは避けなければなりません。
英語が世界の共通語のようになったのは、それが最も美しい言語だったからではありません。それを話す国が、世界を支配していたからです。
現代社会において、英語は「世界をつなぐ言語」であることは間違いありませんが、それは同時に、「世界を蹂躙した言語」でもあります。
英語を話すことで「世界とつながる」という事実は確かにあります。けれど同時に、「誰かの言葉と記憶を踏みつけた足跡の上を歩いている」ことも、私たちは決して忘れてはならないのです。
土地に属するという思想


タロンガ動物園では、案内や展示にアボリジナルの言語を使い、「土地に属する」という価値観を伝えていました。西洋では土地は所有物ですが、アボリジナルにとって土地は「自分たちが属する存在」です。
私は長年、土地は所有するものと疑わずに生きてきました。しかし、その考えが自然ではなく、誰かが意図的に植え付けたものだと気づきました。
そこから何を学ぶか

オーストラリアの歴史は、武力と制度によって文化や言語を塗り替えることが可能であることを示しています。そして、その影響は数百年経っても消えません。
英語を学ぶこと自体はとても良いことです。しかし、その言語がどう広まったのか、その背後にどんな歴史があったのかを知らずに使うのは危ういことだと思います。土地も文化も言葉も、意図すれば奪える──それを知ることは、私たちが何を守るべきかを教えてくれます。
美しい景色に酔うだけでなく、その裏にある物語に目を向けること。この旅は、私にその姿勢を深く刻みつけました。そして、これからも問い続け、学び続け、自分が属する土地と文化を誇りとして生きていきたいと思います。
カテゴリ
人気記事
当社の「従業員」の定義
当社では「従業員」を“理念やクレドに従う全スタッフ”と定義しています。
つまり一般的な社員だけでなく、アルバイトさん、パートさん、
そして経営トップや役員も従業員の一人であり、そこに優劣はありません。
一般的には、経営者に「従う」という意味で従業員という言葉が使われていますが、
当社では理念やクレドに「従う」という意味で、
経営トップも含めて関係者全員を従業員と定義しているのです。
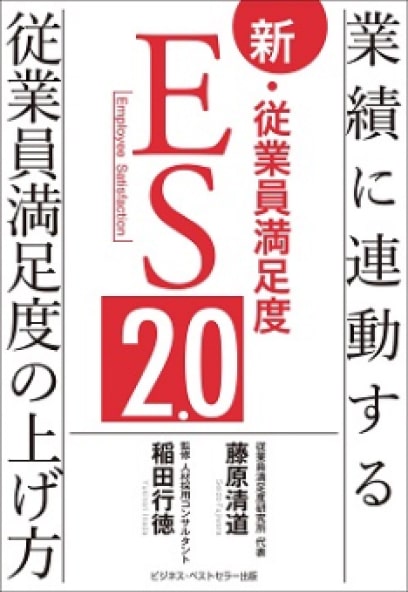
手軽に学び始めたいという方はこちら
日本で唯一の
ESに特化したメルマガ
2008年の創刊以来、毎日配信し続け6230号。
採用や組織作りを中心とした現役経営者の思考を学べる
1ヶ月間無料の日刊の会員制メールマガジンです。
サービスについてご質問などがございましたら、こちらからお問い合わせください。
お問い合わせはこちら