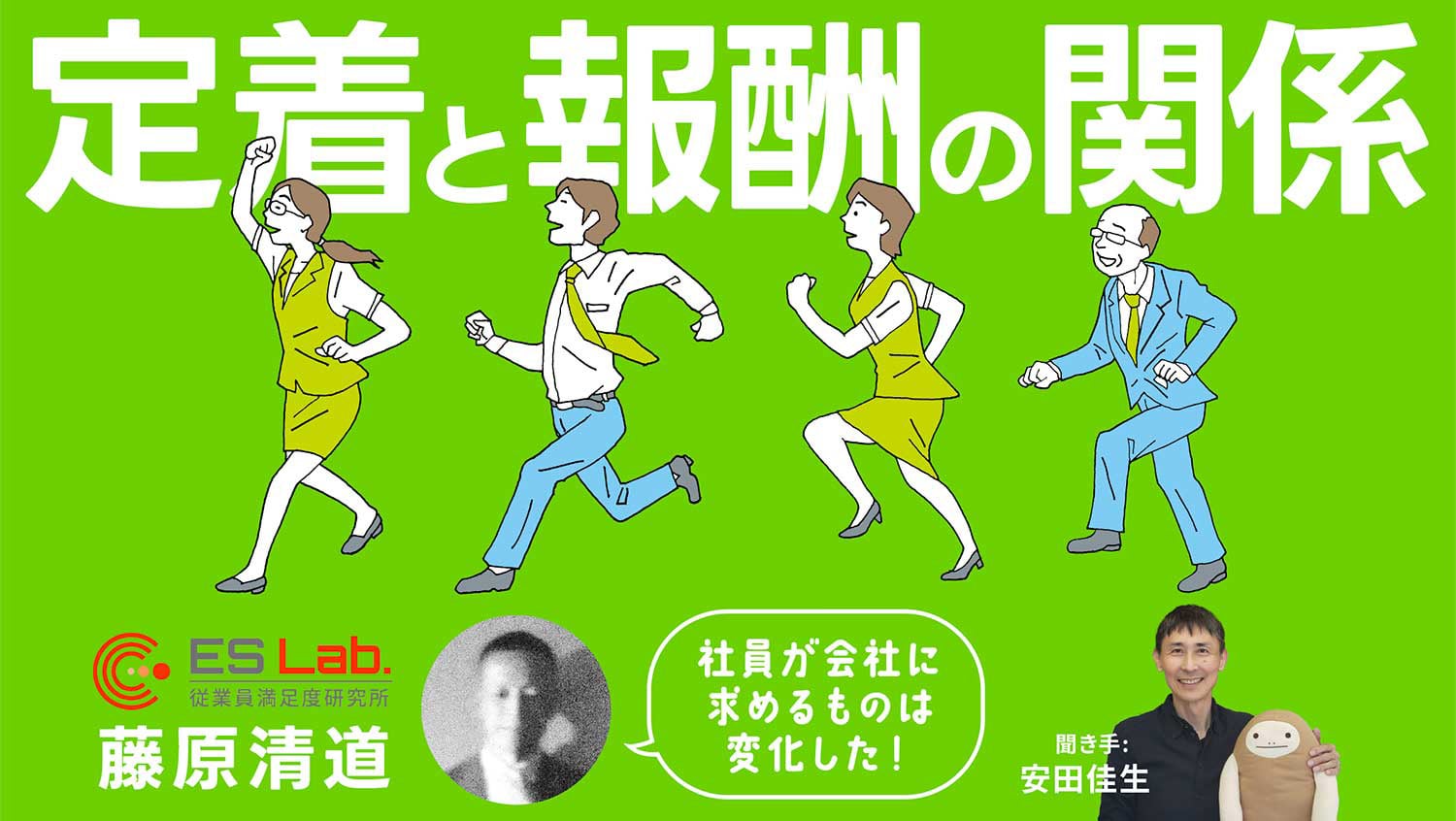安田佳生さんとの対談 76【形骸化しないクレドの作り方】
人は何のために働くのか。
仕事を通じてどんな満足を求めるのか。
時代の流れとともに変化する働き方、そして経営手法。
その中で「ES(従業員満足度・従業員エンゲージメント・ウェルビーイング)」に着目し様々な活動を続ける従業員満足度研究所株式会社 代表の藤原 清道が、株式会社ワイキューブ創業者の安田佳生さんと対談しています。
雇わない株式会社というユニークな会社の取締役も務め、「雇わない経営」を標榜する安田さんと、ESの向上を使命に事業展開する私(藤原)の対談を、ぜひ読んでいただければと思います。
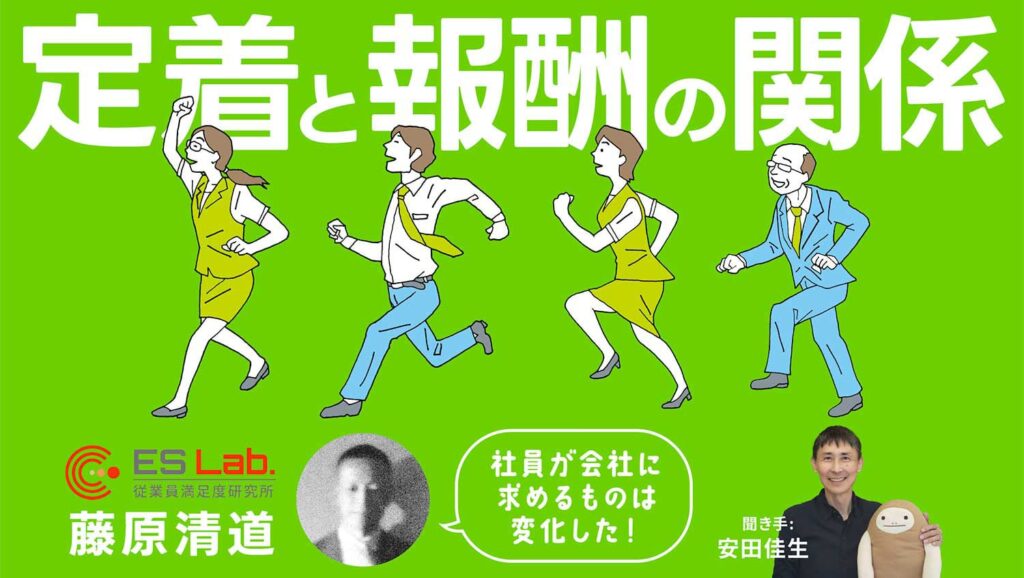
欧米発の“クレド”を、そのまま導入しても意味がない理由
クレド(CREDO)は、もともとリッツ・カールトンやジョンソン・エンド・ジョンソンのような欧米企業で活用されていた「行動指針カード」です。
日本でも一時期話題になり、クレドを導入する企業が増えましたが、実際にクレドが機能して組織が良くなったという事例には、私は出会ったことがありません。
その理由の一つは、クレドが生まれた背景にある宗教観・労働観の違いにあります。
クレドを支える「宗教観」と「労働観」の違い
クレドが生まれた欧米社会の基盤には、キリスト教があります。
一方、日本人の多くは無宗教だと自認しながらも、実際には神道や仏教の価値観が深く根づいています。
以下に、日欧の労働観の違いをまとめてみましょう。
| 視点 | 日本(神道的) | 欧米(キリスト教的) |
|---|---|---|
| 労働の起源 | 神様からの恵み | 神様からの罰(原罪) |
| 職場の意味 | 神聖な場所 | 苦役を果たす場所 |
| 休日の考え方 | 平日と区別しない | 苦役からの解放・神聖な日 |
日本では、仕事とは「社会に役立つこと」「誰かのために尽くすこと」というポジティブな意味合いが強く、労働=罰ではありません。
そのため、欧米で機能していたクレドをそのままコピーしても、日本の組織では根づかないのです。
日本人の価値観に合わせたクレドが必要
私自身もかつて欧米型クレドを導入しようとして、うまくいかなかった経験があります。
だからこそ、「日本人らしさ」に合ったクレド設計と浸透方法が必要だと痛感しました。
私が実践しているクレドづくりは、欧米型をベースにしながらも、
- 日本人の労働観
- 日本独自の組織風土
- 「共に生きる」という価値観
に合わせて、設計思想から根本的に見直したものです。
なぜクレドは形骸化するのか?その答えは価値観にある
クレドが「飾りのカード」で終わってしまう原因は、その企業文化や人々の価値観にフィットしていないからです。
どんなに美しい言葉でも、浸透しなければ意味がありません。
対談では、
- なぜ多くのクレドは形骸化するのか?
- どうすれば日本人の組織に本当に機能するクレドがつくれるのか?
について、率直に語り合っています。
ぜひ一度、ご覧ください。
🔗 【形骸化しないクレドの作り方】対談記事を読む
興味のある方へ
対談では語りきれなかった内容も多くあります。
「形骸化しないクレドをつくりたい」「経営理念を本当に機能させたい」
そう感じられた方がいらっしゃいましたら、無料で読める解説記事や事例紹介もご案内できますので、ぜひお気軽にご連絡ください。
以下をクリックして、対談内容をチェックしてみてくださいね!
【形骸化しないクレドの作り方】
安田佳生 ✕ 藤原清道 連載対談 第76回
カテゴリ
人気記事
当社の「従業員」の定義
当社では「従業員」を“理念やクレドに従う全スタッフ”と定義しています。
つまり一般的な社員だけでなく、アルバイトさん、パートさん、
そして経営トップや役員も従業員の一人であり、そこに優劣はありません。
一般的には、経営者に「従う」という意味で従業員という言葉が使われていますが、
当社では理念やクレドに「従う」という意味で、
経営トップも含めて関係者全員を従業員と定義しているのです。
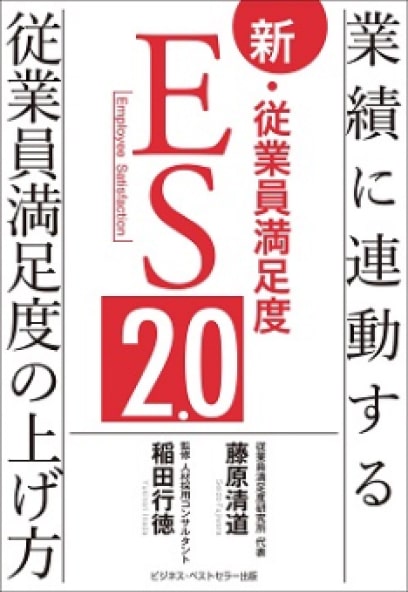
手軽に学び始めたいという方はこちら
日本で唯一の
ESに特化したメルマガ
2008年の創刊以来、毎日配信し続け6230号。
採用や組織作りを中心とした現役経営者の思考を学べる
1ヶ月間無料の日刊の会員制メールマガジンです。
サービスについてご質問などがございましたら、こちらからお問い合わせください。
お問い合わせはこちら