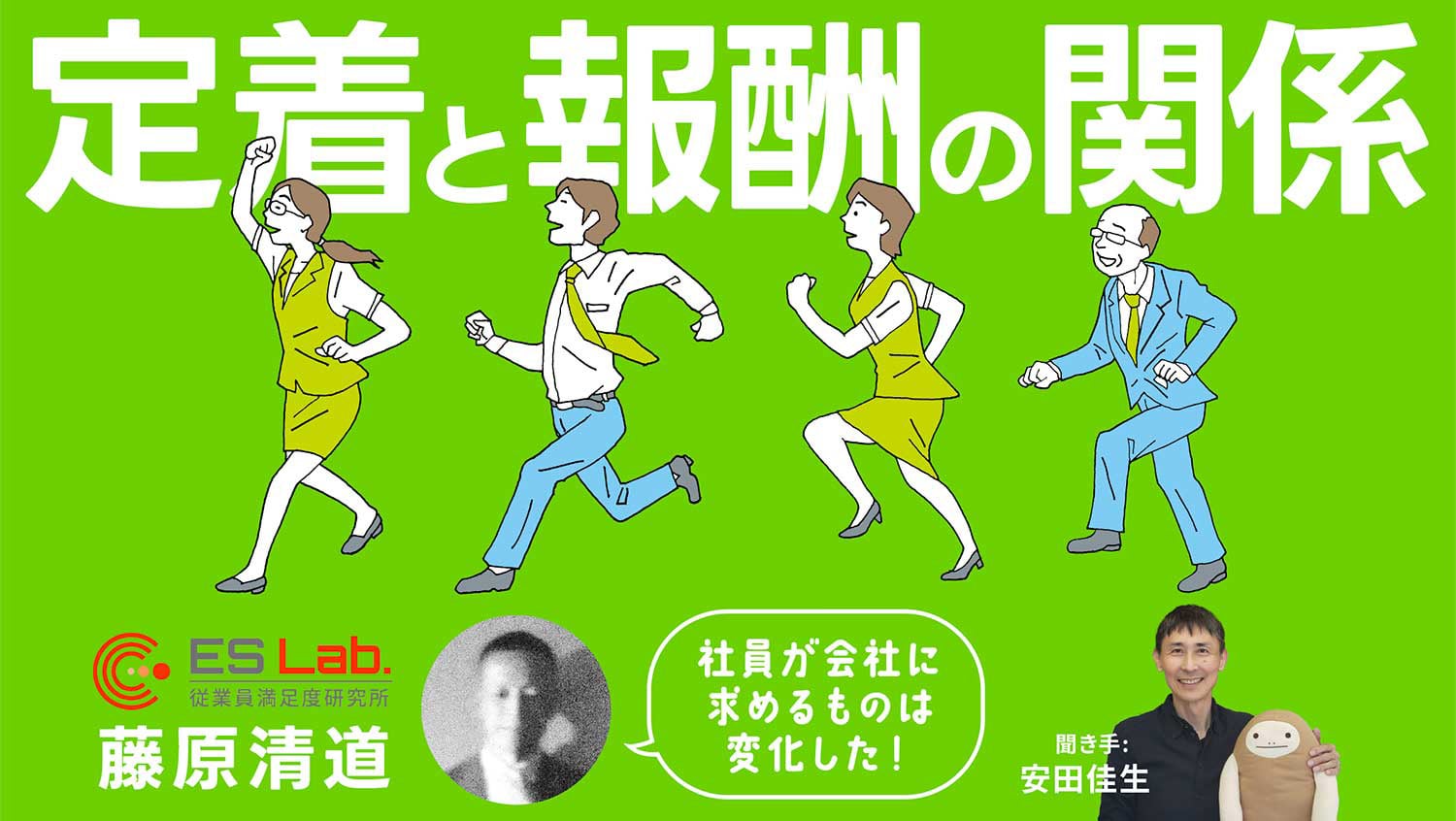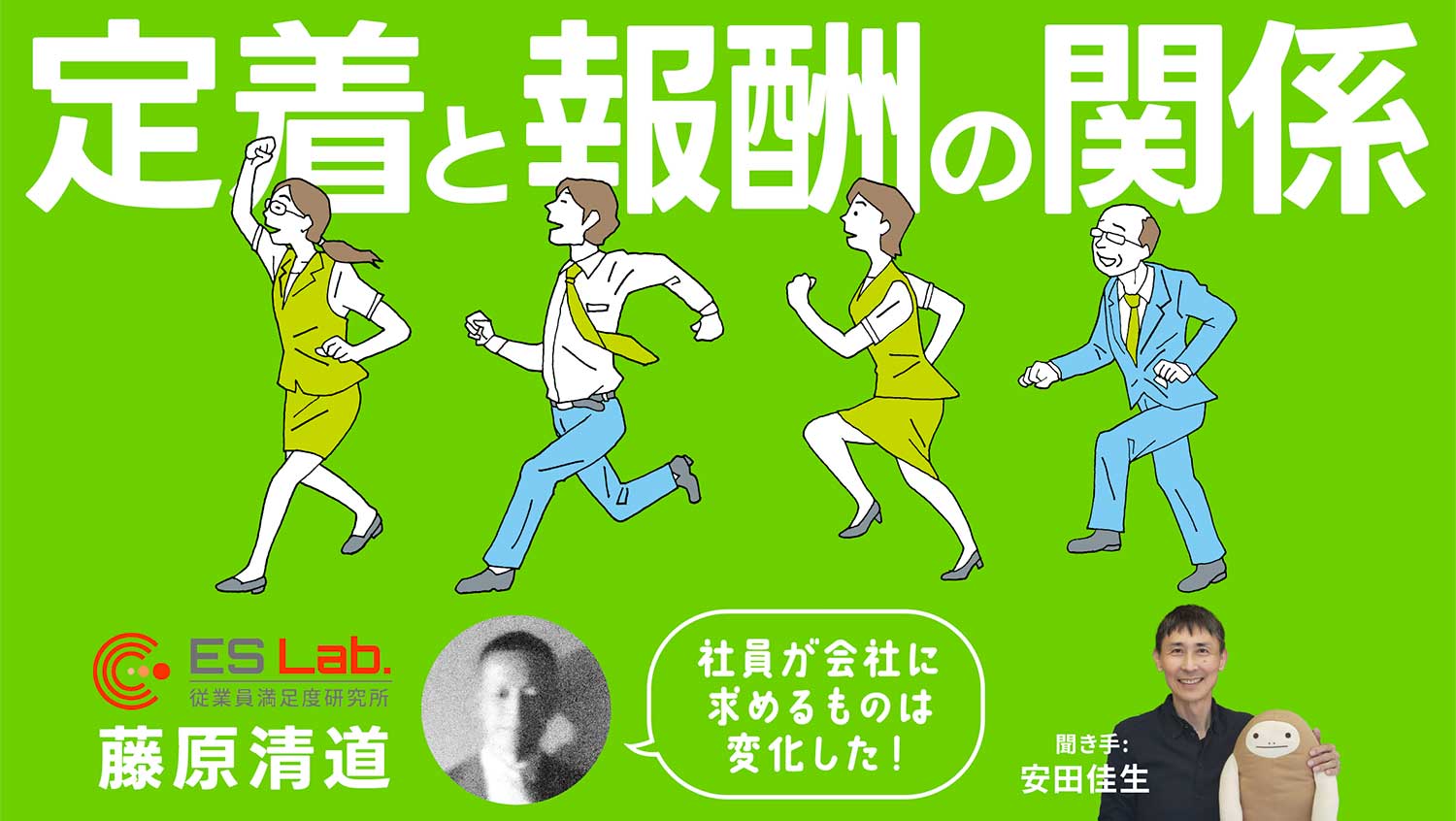
元ワイキューブの社長で境目研究家 安田佳生さんとの対談企画
人は何のために働くのか。
仕事を通じてどんな満足を求めるのか。
時代の流れとともに変化する働き方、そして経営手法。
その中で「ES(従業員満足度・従業員エンゲージメント・ウェルビーイング)」に着目し様々な活動を続ける従業員満足度研究所株式会社 代表の藤原 清道が、安田佳生さんと対談していきます。
雇わない株式会社というユニークな会社の取締役も務め、「雇わない経営」を標榜する安田さんと、ESの向上を使命に事業展開する私(藤原)の対談を、ぜひ読んでいただければと思います。
第55回目は【採用商材の常識を覆す鍵は定着力にあり】という内容です
経営者が学ぶべき採用と組織づくりの本質—27年の試行錯誤から得た成功法則
私(藤原清道)は、現在経営歴27年ほどになります。
過去にはさまざまな事がありました(詳細はプロフィールページに書いています)が、自社の採用や組織づくりに向き合い続け、試行錯誤を繰り返して、最善と思われる行動と改善を繰り返したことで、自社にとっての優秀な人材を採用し、その人材が成長しながら、そして成果を上げながら定着するという状態を作り上げることができるようになりました。
そして20年近く前に、その私の会社での成功事例を聞いた経営者仲間たちから、採用や組織づくりについて聞かれ、要望に応えていくうちに、その仕事も事業に成長して今に至ります。
ただ人材採用については、独学で試行錯誤をしたわけではなく、20年前の当時からさまざま参考にさせていただいた企業がありました。その一つが、連載対談をしている安田佳生さんが創業された株式会社ワイキューブです。
そしてその後に出会って、採用面接や求人募集手法についてご指導いただいた、社会保険労務士の稲田行徳さんとは、現在は従業員満足度実践塾を一緒に運営しています。
組織づくりや、マネジメントについては、当時は具体的なことで参考にできる会社や人とのご縁がなかったこともあり、ピーター・ドラッカーや稲盛和夫、一倉定などのビジネス書、そして司馬遼太郎などの歴史小説を読んで、独学でやってきました。
学び始めた当初は、組織開発や人材採用などを私自身が仕事にするつもりは全くありませんでした。ただただ、自分が経営する会社組織をより良い状態にしたいという強い思いから、学びと行動を繰り返してきたに過ぎません。
それが、メールマガジンを発行しはじめて少し経った頃(15年くらい前)から、「組織開発、組織改革を手伝ってほしい。手伝うのが無理ならアドバイスだけでもほしい」というご連絡をいただくことが少ないながらも出始め、そうしたことを仕事としても取り組むようになったのです。
「採用成功=定着成功」ではない!企業が本当に取り組むべき組織づくりの戦略
組織開発、組織改革については、自分が経営する会社で積み重ねてきたことがたくさんありましたので、ご依頼いただいた企業にその部分で価値提供をすることは最初からスムーズにできました。
ただ、「採用」については、自分は安田さんや稲田さんなどのプロから学んだことを実践しているに過ぎず、学びの内容を自社に最適化するために多少アレンジすることはあっても、その基礎は自分で生み出したものではないため、私が誰かに採用を教えられるという意識は、当時は持っていませんでした。
それが、様々な会社の組織づくりの支援をしていくプロセスで、自社がそうであったように、採用と組織づくりはどこかで線引して切り分けることは困難で、採用力をあげたいならES(従業員満足度・従業員エンゲージメント・ウェルビーイング)を高める組織づくりが欠かせないし、いい組織づくりを推進したいのなら人材採用にも同時に向き合う必要があり、それをやり続けてきた結果、採用と組織づくりの両面での仕事を期待され、また依頼されるようになってきたのです。
しかし、私は「人材採用」を単体でお仕事を受けることはありません。
あくまでも、ESの高い組織づくりをしていくプロセスの一部として、採用力の向上が欠かせないからその部分も合わせて担っていくという考え方でやっているだけで、採用だけを成功させても、組織にとって良い状態は作れないと、私は考えて自らの仕事に向き合っています。
人材業界の歪みと企業の採用戦略—定着率を上げる採用DXの本質とは?
昨年一緒に仕事をさせていただいた人材業界の方が、「人材業界は、やっていることが昔(30年くらい前)から全く変わっていない」とおっしゃっていたことが、今でも記憶に残っています。
具体的な手法は、就職情報誌という分厚い紙媒体を使っていた時代から、採用のDX化が進んでAIも活用するような時代に移行して、手法そのものは大きく変わっていますが、やり方の本質は30年前から全く変わっていないということです。
人材採用事業を展開している多くの企業のビジネスモデルは、クライアント企業の採用部分だけを成功させれば儲かるということになっていて、その数が多ければ多いほどより儲かります。
しかし、団塊ジュニア世代の新卒をピークにして、そこからは右肩下がりに新卒採用マーケットが縮小し続けたのに、人材業界各社は、事業規模を小さくしたり事業転換をするところがあまりなかったことから、この業界に歪みが生まれます。
今も昔も企業では、いい人材を採用したら、その人材に定着してもらって活躍してもらいたいわけです。
しかし人材業界の各社は生産年齢人口が減り続ける現状の中で、自社の売上を伸ばし続けようと思ったらどうするか。転職マーケットの市場規模を増やす必要があります。
つまり、人材がどこかの企業の入社しても定着せずに、転職を繰り返してもらったほうが儲かるという状態になったため、大きな声では言えないけれど、その業界で仕事をしている会社にとっては、日本中の会社で定着率が高まらないほうが、自社のビジネスにとって望ましい状態ということになってしまったわけです。
この状態を変革する第一歩として、安田さんと一緒に商品開発をしました。
その開発背景を知っていただけるような今回の対談です。
よかったら読んでみてくださいね。
以下をクリックして、対談内容をチェックしてみてくださいね!
【採用商材の常識を覆す鍵は定着力にあり】
安田佳生 ✕ 藤原清道 連載対談 第55回目
カテゴリ
人気記事
当社の「従業員」の定義
当社では「従業員」を“理念やクレドに従う全スタッフ”と定義しています。
つまり一般的な社員だけでなく、アルバイトさん、パートさん、
そして経営トップや役員も従業員の一人であり、そこに優劣はありません。
一般的には、経営者に「従う」という意味で従業員という言葉が使われていますが、
当社では理念やクレドに「従う」という意味で、
経営トップも含めて関係者全員を従業員と定義しているのです。
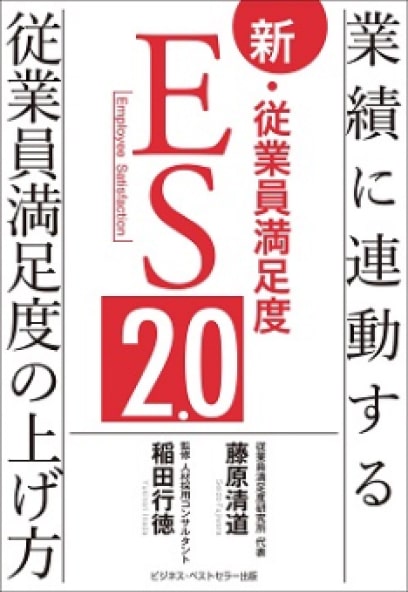
手軽に学び始めたいという方はこちら
日本で唯一の
ESに特化したメルマガ
2008年の創刊以来、毎日配信し続け6400号。
採用や組織作りを中心とした現役経営者の思考を学べる
1ヶ月間無料の日刊の会員制メールマガジンです。
サービスについてご質問などがございましたら、こちらからお問い合わせください。
お問い合わせはこちら