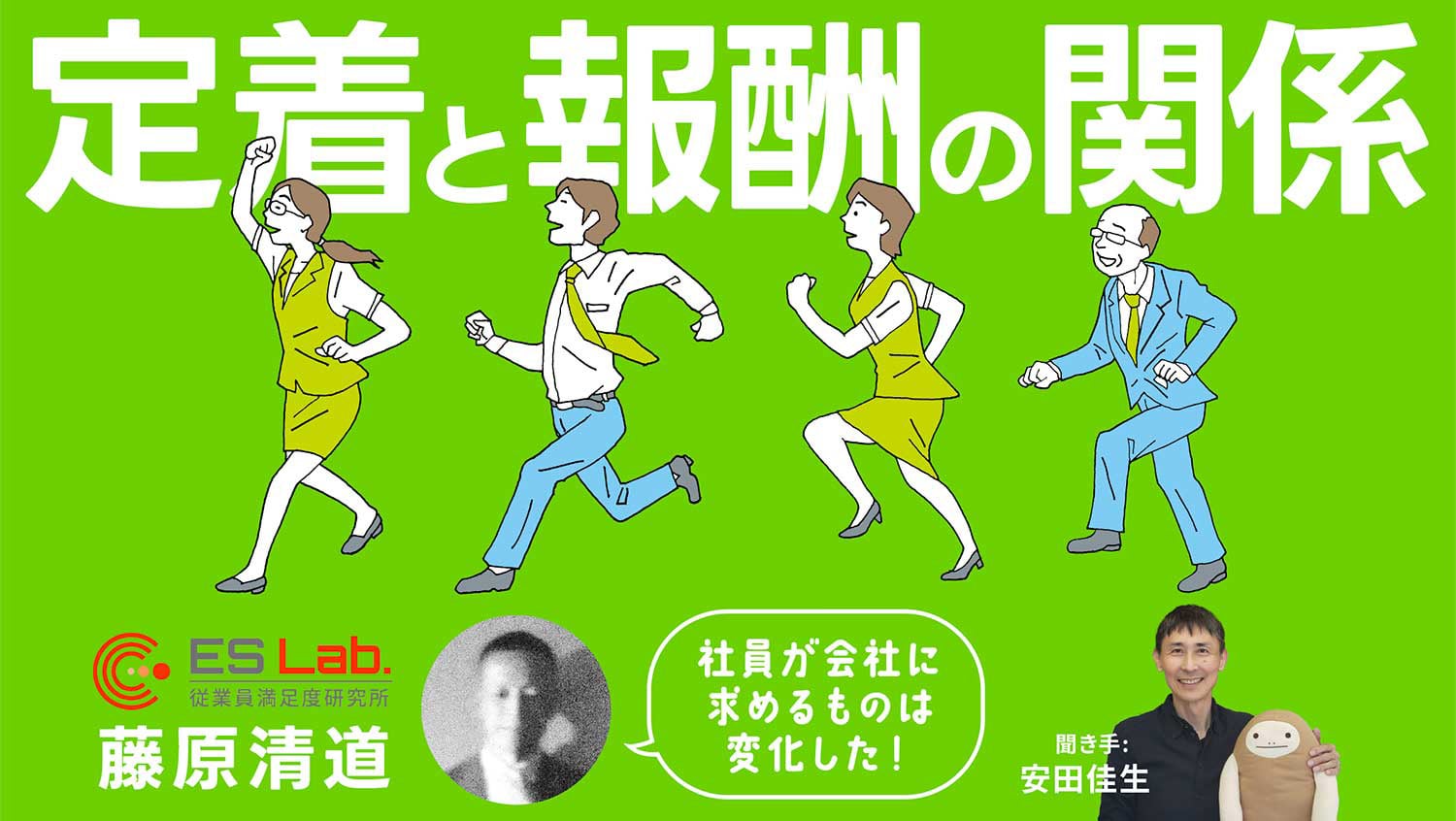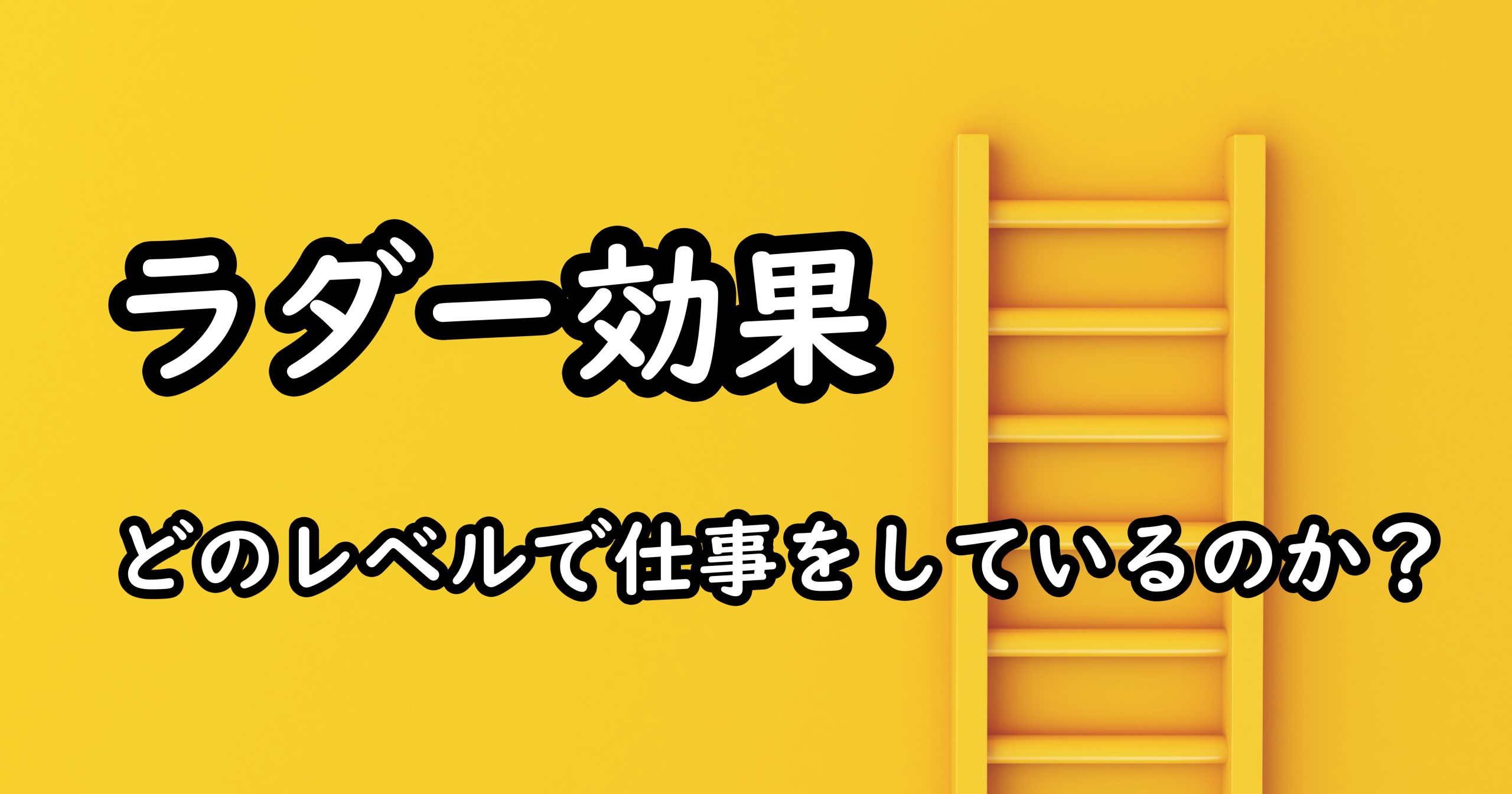
毎日毎日、いろんな場所で、いろんな話を見聞きします。
本を読んだり、他人から聞いたり・・・
そして、いろんな話に出あったときに、人はよくこんな言葉を口にします。
「 なぁんだ~
その話なら知っているよ 」
しかし、この言葉が頭をよぎったら要注意です。
目の前にある有益な情報を自らの血肉にできるかどうか
それは自分自身の心の持ち方次第ということに、
お恥ずかしながら、今日改めて気付きを得ることができた藤原です。
今日(3月28日)、年度末の最終日曜日に
どこからそんな気付きを得たのか、まずはその“気付き元”を紹介したいと思います。
【以下、株式会社リンクアンドモチベーション様発行の『Link Express vol.9』より引用】
■ラダー効果■
意義と価値を見出す技術
毎日の業務の繰り返しに、「何のために、こんな仕事をしているんだろう」とやる気を失ってしまう人がいます。しかし仕事の意味は、その捉え方次第なのです。今回はこうした行動の意義や価値を見出す技術として、「ラダー効果」という手法を紹介します。
では逸話を例にとって説明していきましょう。
ある時、旅人が石を積んでいる職人A、B、Cに出会いました。旅人が「何をしているんですか?」と一人ひとりに質問したところ、職人Aは「石を積んでいる」と答え、次に職人Bは「教会を造っている」と答えました。そして最後の職人Cはこう答えました。「人々の心を癒やすための仕事をしている」と。
職人A、B、Cはすべて、「石を積む」という同じ仕事をしていますが、質問に対する回答はそれぞれ異なっています。職人Aは「石を積んでいる」という“行為”を、職人Bは「教会を造っている」という“目的”を、職人Cは「人々の心を癒やすための仕事をしている」という“意味”を答えているのです。では、この中でどの職人が、自分の仕事にやりがいを持ち、質の高い仕事をしているのでしょうか。当然、答えはCです。職人Cは、自分の仕事の必要性を認識し、その意義と価値を見出して取り組んでいるので、ゴールに向かってまい進することができます。一方、職人Aは仕事を行為レベルで捉えているため、その目的を把握できず、この仕事に時間を費やすにつれて不満が募りかねません。この「石を積む」に似た行動は、私たちの生活の中にもたくさんあります。たとえば、ある日の夕飯づくり。「夕飯をつくっている」という行為レベルか、「家族の栄養バランスを支えている」という目的レベルか、それとも「家族がずっと幸せに過ごせるように健康を支えている」といった意味レベルか、その捉え方次第で、夕飯づくりに対して湧き出るエネルギーの大きさにきっと違いがあるでしょう。
このように「ラダー効果」とは、まるで梯子を上っていくかのように、視点の抽象度を引き上げて行動の意義や価値を捉えることで、自身のモチベーションを高め、行動のクオリティをも向上させていくという手法です。もし、目の前の仕事に対するあなたのモチベーションが下がっているとしたら
・・・抽象度の梯子を一段ずつ上り、「誰の役に立つのか?」、「社会的な影響は?」など、その仕事の意味を自分に対して問いかけてみましょう。仕事を行為レベルで捉えるのではなく、その意味とのつながりを見出すことができれば、取り組む姿勢も前向きになり、行動が変わってくるはずです。意識して訓練すれば、この思考は身につけることができます。「ラダー効果」を上手に使ったモチベーションコントロール、ぜひ試してみてください。
というお話。
上記のコラムのふたつ目のブロック(5行目~18行目)までは、非常に有名なお話ですので、多くの方が知っていらっしゃることと思います。
しかし、知っているだけでは実はあまり役に立ちません。
もし知っているだけで役に立つのだとしたら、この話をしっている人が経営者を務める会社では、全従業員が仕事を意味レベルで捉えられるように
なっているはずです。
そして、全従業員が毎日イキイキと楽しく、高いモチベーションで働くことができているはずです。
結局、どんなでも、経営者が知っているだけで、現場にその知識や想いが浸透していなければ、そのことを知らないことと同じか、知らないよりも悪いことだと思います。
(知っているのに伝えるきることができていないということですから。)
というのは実は私自身の話。
弊社のスタッフ全員をあらためてみて、
「石を積む」という行為レベルで仕事をしているのか
「教会を造る」という目的レベルで仕事をしているのか
「人の心を癒やす」という意味レベルで仕事をしているのか
と考え、
う~ん。。。
私自身の至らなさを痛感、そして深く内省した次第です。
みんながどういうレベル(行為・目的・意味)で仕事をしているのか、これは仕事をしている最中や終わった後の仲間の表情をみればすぐに分かります。
表面上は同じ仕事をしていたとしても、
疲れた表情や、楽しくなさそうな表情が出ていれば、それは「行為レベル」または「目的レベル」で仕事をしているということですし、
充実感のある輝いた表情が出ていれば、それは「意味レベル」で仕事をすることができているということになります。
そんなことを改めて考えたときに、この有名な教会の話を、
「なぁんだ~
その話なら知っているよ」
では片付けられないことに気付かされたのです。
結局、自分が知っていても、みんなに伝わっていないのですから…(反省)
それは一にも二にも、私の責任。
おそらく私自身が、「意味レベル」での仕事がしきれていなかったことと、「行為レベル」で仕事をする人たちに、その意味をしっかり伝えることができていなかったのだということです。
この記事を読んでくださっている経営者のみなさん、
御社の従業員のみなさんは、疲れた表情で仕事をしていませんか?
もしそうだとしたら、「行為レベル」「目的レベル」で仕事をさせてしまっているあなたにに責任があると思って間違いありません。
なんて、他人のことを言う前に、私自身が自らやるべきことをやらねばなりません。
経営者から新入社員まで、弊社の仕事に携わる全ての人たちが、「意味レベル」での仕事ができるようになったとき、従業員満足度世界一の組織へ一歩近づくのではないかと思います。
▼本質を見抜く力を身につけるために▼
もっと本質に掘り下げた詳しい話に興味がある方は
著書「新・従業員満足度 ES2.0」か、
以下の日刊メルマガへどうぞ
▶ 名言から学ぶ組織論
カテゴリ
人気記事
当社の「従業員」の定義
当社では「従業員」を“理念やクレドに従う全スタッフ”と定義しています。
つまり一般的な社員だけでなく、アルバイトさん、パートさん、
そして経営トップや役員も従業員の一人であり、そこに優劣はありません。
一般的には、経営者に「従う」という意味で従業員という言葉が使われていますが、
当社では理念やクレドに「従う」という意味で、
経営トップも含めて関係者全員を従業員と定義しているのです。
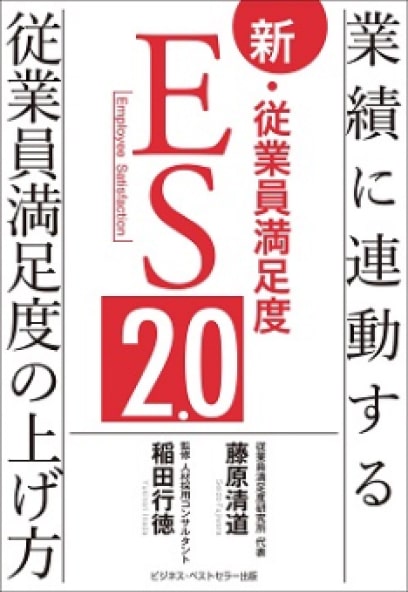
手軽に学び始めたいという方はこちら
日本で唯一の
ESに特化したメルマガ
2008年の創刊以来、毎日配信し続け6190号。
採用や組織作りを中心とした現役経営者の思考を学べる
1ヶ月間無料の日刊の会員制メールマガジンです。
サービスについてご質問などがございましたら、こちらからお問い合わせください。
お問い合わせはこちら