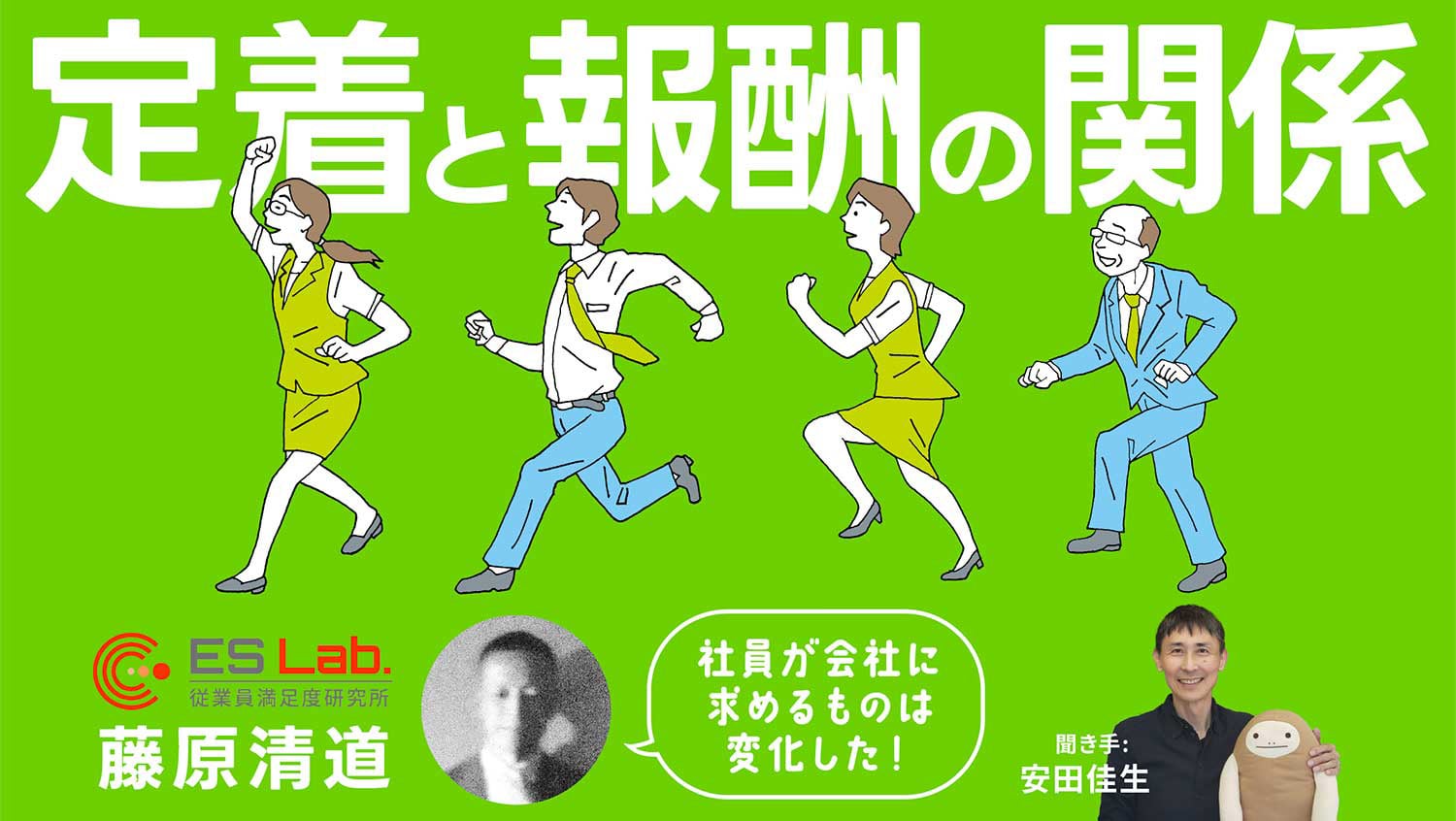安田佳生さんとの対談 74【本当に守るべきは社員ではなく社長自身】
人は何のために働くのか。
仕事を通じてどんな満足を求めるのか。
時代の流れとともに変化する働き方、そして経営手法。
その中で「ES(従業員満足度・従業員エンゲージメント・ウェルビーイング)」に着目し様々な活動を続ける従業員満足度研究所株式会社 代表の藤原 清道が、株式会社ワイキューブ創業者の安田佳生さんと対談しています。
雇わない株式会社というユニークな会社の取締役も務め、「雇わない経営」を標榜する安田さんと、ESの向上を使命に事業展開する私(藤原)の対談を、ぜひ読んでいただければと思います。
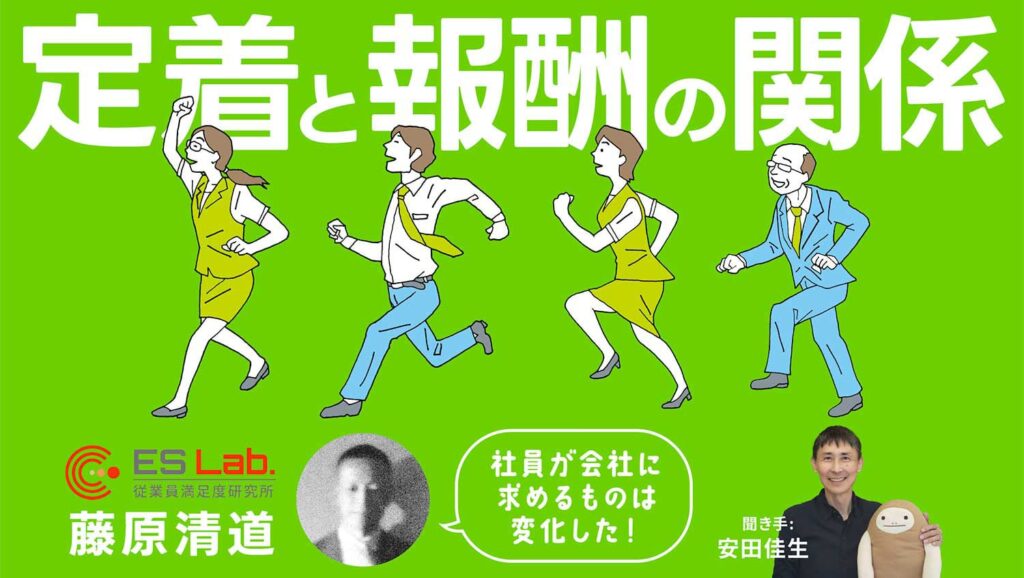
「社員を守る」という言葉の意味を、あなたは本当に理解していますか?
「社員を守る」とは、いったい何を意味するのか?
そんな問いを胸に、今週の安田佳生さんとの対談をお届けします。
今回の対談テーマは、【本当に守るべきは社員ではなく社長自身】
このテーマにピンときた方は、きっと「守る」という行為の本質をすでに直感しているはずです。
「雇用=守る」ではなくなった時代
社員の雇用を維持することが、イコール社員やその家族の人生を守ることに繋がっていたのも今は昔。
会社が潰れたら社員が路頭に迷うと本気で考えている経営者やリーダーがいまだに存在していますが、実際には会社が潰れても現代の日本においては路頭に迷いません。
しかし、「給料はたっぷり出しているけど、重要な仕事はさせていない」というような会社の場合、その環境に甘んじている従業員は人間力の基礎(自分の力で自分の人生を豊かにしていく力)が、月日の経過とともに劣化していきますから、急に会社が無くなったら、それまでと同じ収入を得られる仕事を得ることができない現実に直面して、一時的にかなり困惑状態になるとは思います。
それでも、日本国内で生きている限り、本当に路頭に迷うようなことはありません。
本当に社員を守りたいなら「力を育てる」ことに舵を切れ
「いやいや、そうは言っても、うちの会社が潰れたら社員は実際には困ると思うよ。再就職先だってすぐに見つからないかもしれないし」
と思う経営者の方も少なくないかもしれません。実際には。
しかし実際にそうなのだとしたら、ES(従業員満足度・従業員エンゲージメント・ウェルビーイング)の低い組織である可能性が高い。
また、雇用されている側の社員という立場で仕事をしている人の中にも
「いやいや、そうは言っても、会社が潰れたら困る。年齢的に再就職も簡単じゃないし」
と思う人もいるかもしれません。
実際にそうなのだとしたら、環境に甘えることが常態化していて、人間力の基礎が劣化している可能性が高い。
今は、仕事の本質(誰かの役に立つこと)が分かっていて、本質に沿ったことができる人であれば、年齢や性別などは一切関係なく、本人の特性や能力に合わせて仕事は選び放題な状態です。
「辞めやすいけれど、辞めない組織」をつくる
そういう世の中の現状を理解した時、経営者の立場で、本当の意味で「従業員を守りたい」と思うのなら、雇用そのものを守るのではなく、従業員一人ひとりが自社に所属して働いている状態でも、辞めて他の会社で働いても、また独立して自分で事業を始めても、一切食うことには困らないような状態に育て上げることを考えるべきです。
「守っているつもり」が、相手の力を奪っていることもある。
私も昔、社員に「優しさ」という名の呪いをかけてしまっていたことがあります。
今までも私はくり返し言ってきたことですが、「辞めやすいけれど人が辞めない組織」というのが、ES向上を追求した先にある究極の形であると考えています。
「辞めやすい」というのは、2つの要素があって、一つは、辞めたいという意思表示をした人に対して、変に引き止めたり、その人の未来を邪魔するような態度を会社が取ることがない状態です。
そしてもう一つは、今の会社を辞めて、転職したとしても独立したとしても同じ水準の報酬を得られるだけの実力がついている状態です。
ESは“力ある人材”を定着させる戦略である
この状態をつくるのが、本当に従業員を守りたいと思っている経営者のやるべきことであって、単に雇用そのものを守って給料を支払い続けることが守ることではありません。確かに以前は、それが「従業員を守ること」だった時代はありますが、今はそんな時代じゃありません。
大企業でも潰れる時代ですし、潰れるまでいかなくても日産自動車のように大規模人員削減が普通に行われることが珍しくなくなりました。
年功序列、終身雇用なんていうことも、とっくにあたり前じゃなくなりました。
だからこそ、私たちはES向上を経営目的の一つに設定し、「辞めやすいけれど人が辞めない組織」を作っていかねばならないのです。
そして、そういう組織を作れないと、働き手から選ばれない組織となり、結果として淘汰されることになります。
お金を稼ぐということだけを考えたら、現在所属している会社で働き続ける必要がまったくないレベルの力がある従業員を、いかにして定着させるか。
それが、私が提唱し続けているESです。
働く理由が「お金だけ」になると人は弱くなる
お金を稼ぐということは働く動機の一つではありますが、あくまでも同期の一部に過ぎません。
仕事の本質に真剣に向き合って、自分を高めることを真摯にやってきた人は例外なく気づくことがあります。
それは、お金のためだけに働いていると、どこかで働くことが嫌になり、自分を磨き高めることよりも、いかにラクしてお金を稼ぐかというマインドに傾倒していくことになるということ。その結果、仕事の本質を忘れて自分の人間力が劣化していくことになることに気づかずに。
年齢と経験を重ねるごとに、仕事が大好きになっていき、どんどん創造的なことをしてパワーアップしてく人と、逆に仕事を好きになれずに早くリタイヤすることがカッコいいと思って、仕事をしなくても成り立つようなことを考えながら生きていく人と、二極化が進んでいきます。
絶対的に正しい生き方というものはありませんので、どちらの生き方を選択しても間違いではありません。
私が経営する組織では、このどちらのタイプの人にとっても、ESの高い組織にすべく挑戦中です。
会社組織がどうなろうが、天変地異が起こってすべてがひっくり返ろうが、経営者も含めた全従業員が、路頭に迷わないような状況をつくり上げていきます。
以下をクリックして、対談内容をチェックしてみてくださいね!
【本当に守るべきは社員ではなく社長自身】
安田佳生 ✕ 藤原清道 連載対談 第74回
カテゴリ
人気記事
当社の「従業員」の定義
当社では「従業員」を“理念やクレドに従う全スタッフ”と定義しています。
つまり一般的な社員だけでなく、アルバイトさん、パートさん、
そして経営トップや役員も従業員の一人であり、そこに優劣はありません。
一般的には、経営者に「従う」という意味で従業員という言葉が使われていますが、
当社では理念やクレドに「従う」という意味で、
経営トップも含めて関係者全員を従業員と定義しているのです。
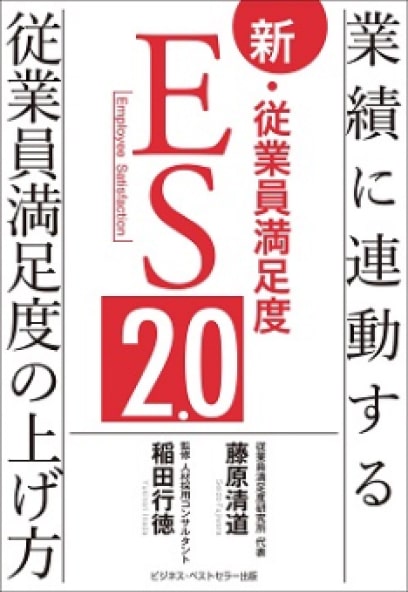
手軽に学び始めたいという方はこちら
日本で唯一の
ESに特化したメルマガ
2008年の創刊以来、毎日配信し続け6230号。
採用や組織作りを中心とした現役経営者の思考を学べる
1ヶ月間無料の日刊の会員制メールマガジンです。
サービスについてご質問などがございましたら、こちらからお問い合わせください。
お問い合わせはこちら